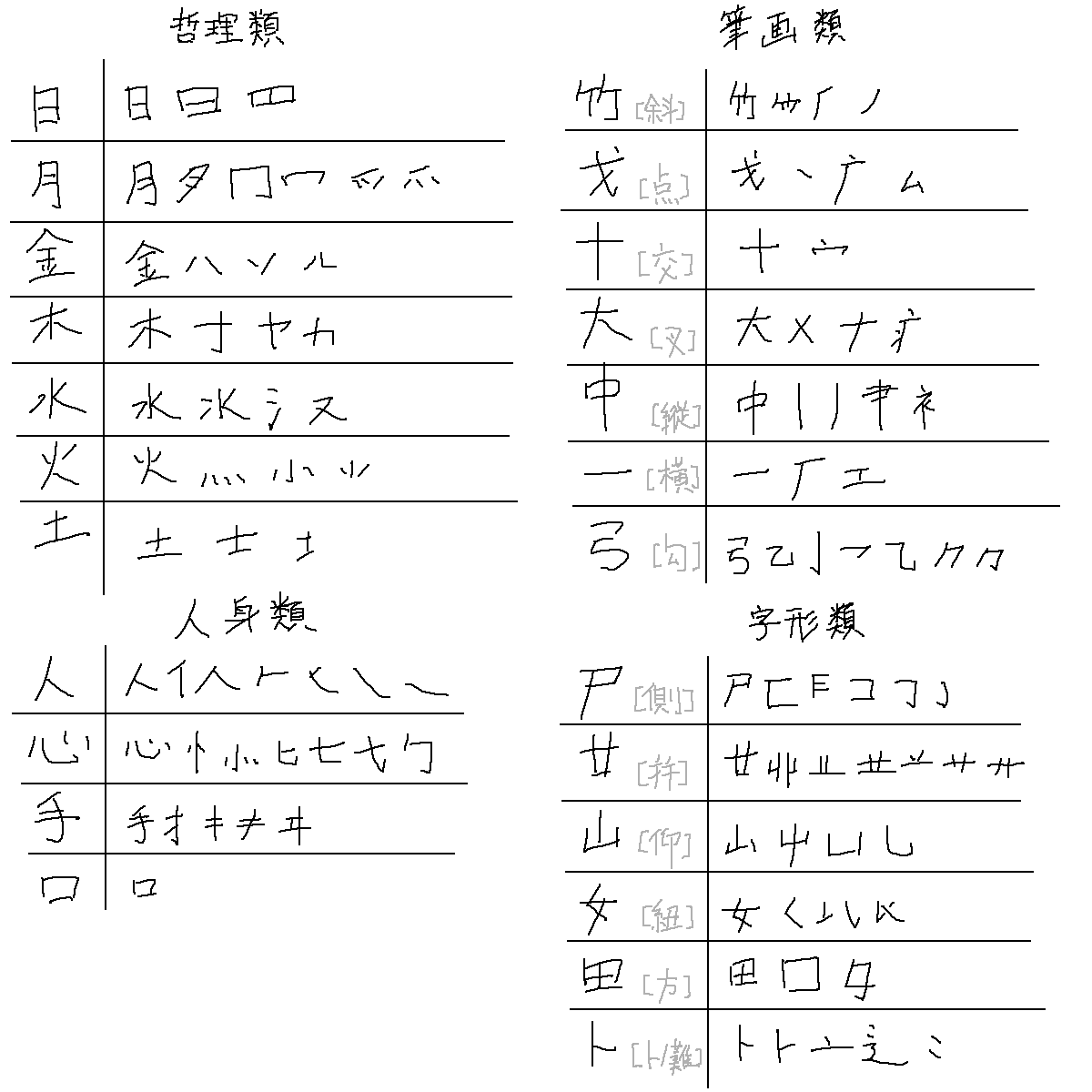
普通話や台湾国語の発音を知らなくても中国語の漢字が打てる方法です。
日本語では「そうけつ」、北京語では「cang jie」、広東語では「chong kit」と読みます。
「如」を「女口」、「旱」を「日一十」などといった要領で入力します。
字形から入力する方法としてはほかにも速成(簡易)倉頡や大易等がありますが、
倉頡が一番基本となる形態で、広く利用可能です。
基本的に繁体字を入力するための方法です。簡体字は打てないことはないですが、重複が多くなってしまったりして、あまり得意ではありません。
現在広く使われている倉頡輸入法には、第三代と第五代の2種類のバージョンがあります。 このページでは、第三代を中心に解説していきます。
倉頡輸入法の基本は、漢字の形状をパターンに分解することです。
倉頡では次に掲げる24種類の字母(字根)が用意されていて、漢字をこれらの字母の組み合わせで表現します。
とはいっても、すべての漢字がこの字母の形状の組み合わせで表現されるわけではありません。
そこで、各字母には簡略化した形である補助字形が用意されていて、この補助字形の形状の部分を対応する字母で表そう、というきまりになっています。
この字母と補助字形を知るのが、倉頡輸入法習得の第一歩となります。
キーボード上では不規則な並びに見えますが、実はグループごとにアルファベット順になっています。
少し複雑ですが、最初のうちはキー配列表と補助字形表を用意しておいて、少しずつ慣れていくと良いでしょう。
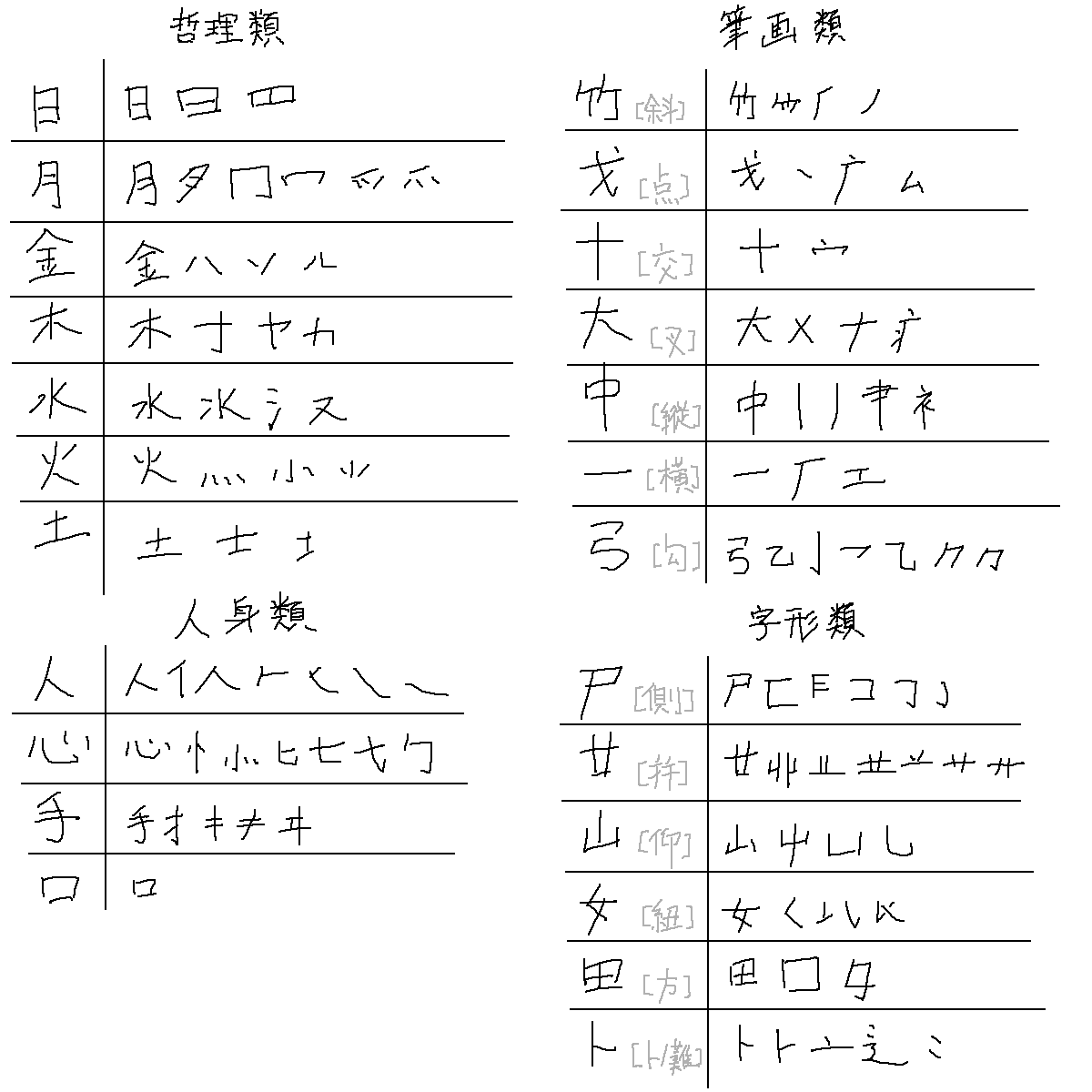
| A 日 | 四角が一本の棒で区切られた形 |
| B 月 | どうがまえ・わかんむり/部首としての「爪」/むじなへんの頭部 |
| C 金 | 八・ソ |
| D 木 | 交差+鉤 |
| E 水 | さんずい/又 |
| F 火 | れっか/「小」の形 |
| G 土 | – |
| H 竹 | 左下へのはらい(ノ) |
| I 戈 | 右下への止め、点(ヽ)/まだれ/ム |
| J 十 | うかんむり |
| K 大 | ナ・メ(斜めの十字)/やまいだれ |
| L 中 | 貫く縦棒/「粛」の上の部分/ころもへん |
| M 一 | がんだれ/工 |
| N 弓 | 鉤・はねを持つ筆画一般(「尸」「山」に属するもの以外)/ク |
| O 人 | 左下へのはらい+接するもう1画/「永」の右側部分の形/右下へのはらい |
| P 心 | 七・ヒ/つつみがまえ |
| Q 手 | 横棒x2+縦に貫く棒(キ) |
| R 口 | – |
| S 尸 | はこがまえ・かくしがまえ/E/コ・「刀」の1画目・「家」の下部のはねる筆画 |
| T 廿 | 縦棒x2+水平線 |
| U 山 | うけばこ、「乱」の右側等の上が開く形 |
| V 女 | 「く」の形/「良」の下半分 |
| W 田 | くにがまえ等の四角く囲む形 |
| Y 卜 | なべぶた/しんにょう/点x2 |
ここでは、倉頡輸入法において、実際に漢字をどのように分解し、入力に使う字母を取るのか、そのルールについて記載します。
倉頡輸入法では、漢字を最大3個のパーツ(字首・字身)に分解して、パーツごとに記号を作ります。
それぞれのパーツごとの最大字母数は漢字の分割数によってかわり、
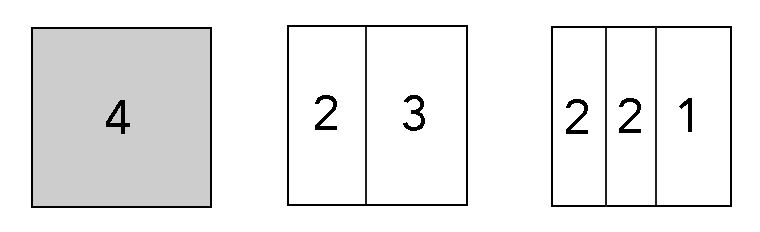
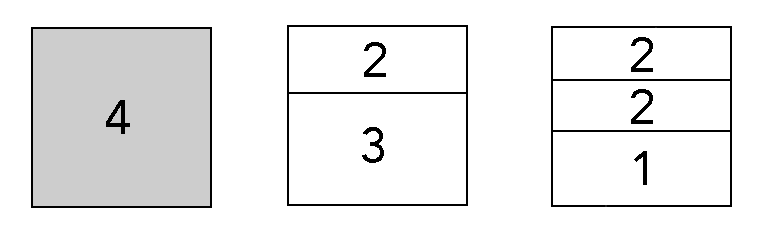
| 連体字(分解なし) | 4 |
| 分体字(2分割) (左–右, 上–下, 外–内) | 2–3 |
| 分体字(3分割) (左–中–右, 上–中–下) | 2–2–1 |
のように作ります。
字母を取る順序は上->下、左->右、外->中です。部首よりも形を優先して見るようにしましょう。
原則として筆順通りですが、たまに例外があります。
例えば「にょう」は左右型に含まれ、「しんにょう」「えんにょう」もほかのにょうと同様に先に取ります。
「うけばこ」も中身の形状によっては外内型となり、先に取る場合があります。(「凶」等)
「甫」等の右上の点は最初に取ります。
ところで、以上の規則に従うと、たとえば「製」のような字は2分割となり、「制」の部分を2字母で作る必要があります。
このように、複雑な字形を作らなければいけないのにかかわらず字母数が限られる場合は、
最初(・二番目・三番目)と最後の部分だけを字母に取ります。
通常ですと「制」は「竹月中弓」ですが、「製」では「竹」と「弓」だけが取られて「竹弓卜竹女」となります(「卜竹女」は衣)。
(さらに言えば、鋭い方は気付かれると思いますが、制の左側、「竹月」も途中の部分、おそらく「手」あたりが省略された形になります)
また、作りたい字そのものが字母(表の左側部分)のなかにある場合は、その字母1個をもって入力コードとしますが、
作りたい字が補助字形の中にある場合は、通常のルールに従って分解して入力します(「又」は「弓大」、「士」は「十一」、etc.)。
(ただし、これ以上分解しようのない文字、例えば「丶」とか「亅」などは例外です)
できるだけ一つの字母に対して漢字の広い部分が対応するように取ります。
卜金」(「戈一竹人」ではない)
木田」(「十田火」ではない)
複数の分解方法があるときは、先に来る字母が漢字のより多くの部分に対応するようにします。
手人」(「一大」ではない)
土口口女」(「十口口女」ではない)
筆画の曲がり等、字形の特徴はなるべく字母に表れるように字母を取ります。
戈弓水」(「戈一水」ではない:二画目の折れを残す)
分体字の一部(字首・字身)の字母を取るとき、最後の字母に相当する部分が「かまえ」の中にある(四方のうち三方以上を囲まれている)場合、 かまえの中身を省略し、かまえ自体を最後の字母とします。 (部首としてのかまえに限らず、あめかんむり等似た形を持つものすべてについて同様です)
女火卜口月」(「女火卜口口」ではない)
一月田」(「一卜田」ではない)
月女女田」(「月女女大」ではない)
一弓中弓」(「一戈中弓」ではない)
尸火尸口口」、「胸」=「月心山大」)。
規則としては前節の通りなのですが、次に掲げるような例外規則があります。
次の9形は単独で用いるときも字首・字身として用いるときも、以下のように符号化します。
| 門 | 日弓
|
| 目 | 月山
|
| 鬼 ※第三代 | 竹戈
|
| 鬥 | 中弓
|
| 隹 | 人土
|
| 阝 | 弓中
|
| 虍 | 卜心
|
| 幾・畿の右上部分 | 女戈
|
| 嬴の上部の「亡口」 ※第三代 | 卜口
|
「大」「木」「火」が文字に大きくかぶさる字形の場合、これらを先に取り、残りの部分を後から取ります。
(例)
| 夾 | 大人人
|
| 夷 | 大弓
|
| 束 | 木中
|
| 東 | 木田
|
| 柬 | 木田火
|
| 棗 | 木月木月
|
| 末 | 木十 (cf. 未=十木)
|
| 秉 | 竹木中
|
| 拳 | 火手手
|
| 脊 | 火金月
|
複雑だったり不規則な形状でどうにも字母を取りにくい場合、「難」(X) を使います。以下の13字が該当します。
| 臼 | 竹難
|
| 肅 | 中難
|
| 齊 | 卜難
|
| 卍 | 弓難
|
| 身 | 竹難竹
|
| 慶 | 戈難水
|
| 龜 | 弓難山
|
| 鹿 | 戈難心
|
| 廌 | 戈難火
|
| 姊のつくり | 中難竹
|
| 淵のつくり | 中難中
|
| 黽 | 口難山
|
| 兼 | 廿難金
|
分体字をパーツに分割する際、以下のものはひとかたまりの字首として扱います。
| 詹のたれ | 弓金
|
| 帝や旁のかんむり | 卜月
|
| 憂の心より上側 | 一月
|
| 產や彥のたれ | 卜竹
|
| 丘 | 人一
|
| 歷や曆のたれ ※第三代 | 一木
|
| 嚢の上部 | 十月
|
| 索のかんむり | 十月
|
上記の方法で記号を構成しても、どうしても重複が出てしまう場合があります(日と曰、酒と洒など)。
この場合、両者を区別するために、片方にX(難)を前置することがあります。
ただしこの仕様は比較的新しく、入力ソフトによっては対応していない場合もあります。
以上、倉頡輸入法の簡単な解説を行いました。慣れないうちは試行錯誤が必要ですが、基本のルールを把握するだけでかなり漢字入力がしやすくなることと思います。 より詳しく知りたい方は、Googleで「倉頡輸入法」と検索すれば中国語・広東語のサイトが多数ヒットするほか、 日本語で解説されているページ(→『倉頡入力法入門』)もあります。
特定の字の入力方法を調べたい場合、Wiktionary (http://ja.wiktionary.org/)
には多くの字の倉頡入力方法が記載されています。また、Mac では中国語入力モード選択時に「尋找輸入碼」(Find Input Code) という機能を使うこともできます。